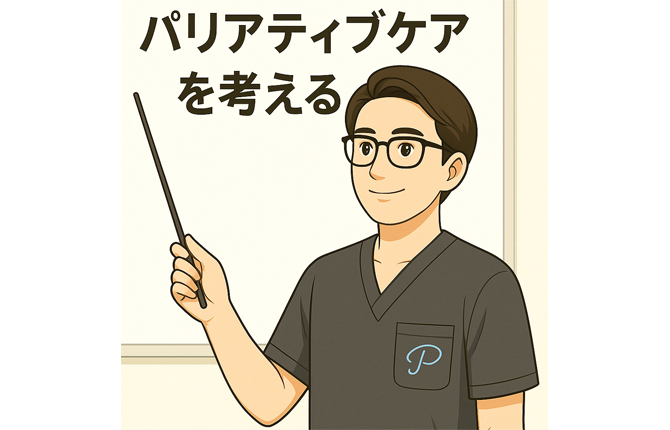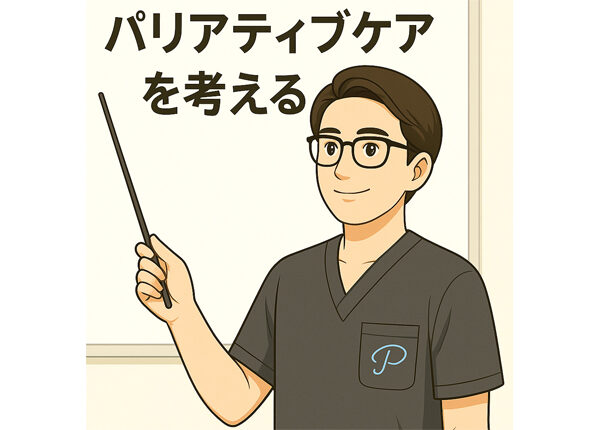リハの介です。
今回は、パーキンソン病の方への具体的なリハビリ内容について少し掘り下げてみます。
パーキンソン病では、身体の動きが鈍くなるだけでなく、嚥下障害(飲み込みにくさ)や構音障害(話しにくさ)など、非運動症状にも注意が必要です。
たとえば――
🔸 PT(理学療法士)は、歩行訓練や転倒予防のための筋力維持・バランス訓練を実施。すくみ足や小刻み歩行に対しては、視覚やリズムを使った誘導も有効です。
🔸 OT(作業療法士)は、食事・トイレ・更衣など、日常生活動作(ADL)の維持を目指します。動作のタイミングや順序を見直すだけで、「できる」が増えることも。
🔸 ST(言語聴覚士)は、嚥下訓練や発声のリハビリを行います。食事中のムセや食後の声のかすれは、誤嚥のサインかも。私たちは超音波エコーを使って、嚥下機能をていねいに評価しています。
そして、ここで大切なのは「リハビリ=訓練」ではないということ。
姿勢や環境のちょっとした調整、福祉用具の工夫でも、生活のしやすさは大きく変わります。
進行性の病気に対して、「何ができるか?」と考えること。
それが、私たちのリハビリの原点です。
次回は、終末期ケアにおける“その人らしい生活”を支えるリハビリについてお話しします。
※本投稿は、一般的なリハビリテーション情報のご紹介です。
症状や対応は個人により異なりますので、必ず主治医やリハビリ専門職にご相談ください。
※このブログは、パリアティブケアホームのInstagramにて投稿したものを再編集してご紹介しています。
📞 ご相談・お問い合わせはこちらから
👉 お問い合わせ | https://minnano-roujinhome-naginoyao.com/contact/
🔗 関連リンク:パリアティブケアホーム専用公式サイト
👉 https://minnano-roujinhome-palliative.com/
🔗 関連リンク:opsolグループ公式サイト
👉 opsolグループ|https://opsol.co.jp/